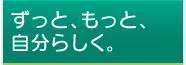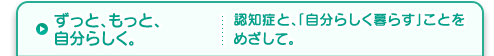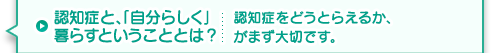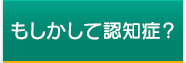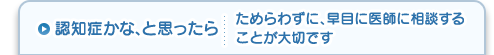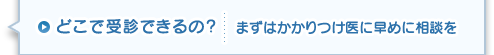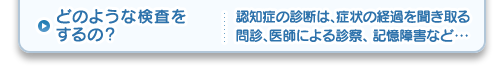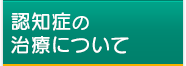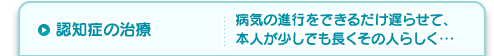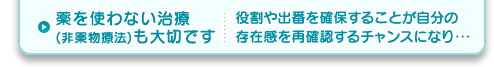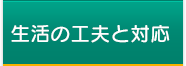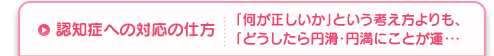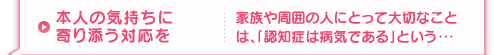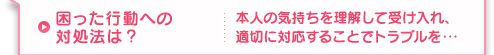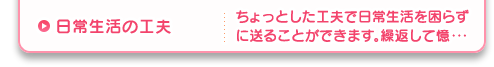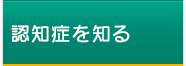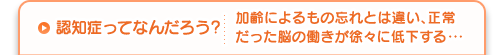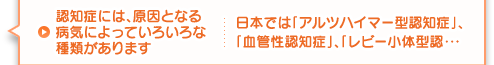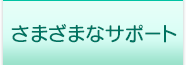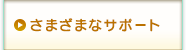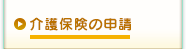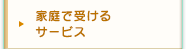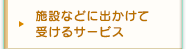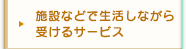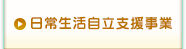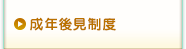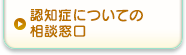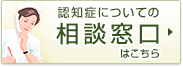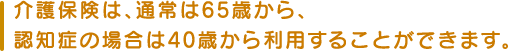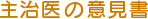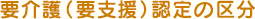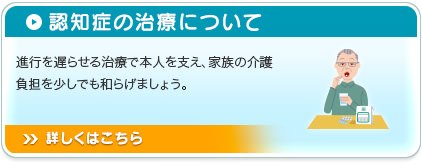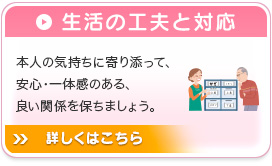介護保険サービスの利用を希望するときは、介護保険を担当する市区町村に申請してください。
※本人や家族が申請できない場合は、地域包括支援センター、居住介護支援事務所、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
![]()

認定調査員が自宅や入所施設を訪問し、本人の心身状態や日常生活の状況などを聞き取り調査します。
主治医からの医学的な意見書の作成を依頼します。
![]()
調査訪問で調査した項目と主治医の意見書をもとに、全国一律の基準で判定します(一次判定)。
その項目のほかに、調査で聞き取った必要な内容を「特記事項」としてまとめます。
![]()
一次判定の結果、主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」で要介護度を判定します(二次判定)。 ※介護認定審査会とは、保健、医療、福祉の専門家で構成された、認定に必要な審査判定を行う市区町村の付属機関です。
| 自立(非該当) | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 |
| 要支援1、2 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
| 要介護1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
| 要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
| 要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
| 要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
| 要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |
![]()
二次判定の結果に基づき、市区町村が要介護(要支援)認定区分などを決定し、申請者に通知します。
![]()
介護や支援の必要に応じて、利用するサービスの種類・回数を決めるケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、サービス提供事業者または介護保険施設などと契約を結び、サービスを受けます。
認知症「いっしょがいいね」を支えるガイドブック(監修:横浜総合病院・横浜市認知症疾患医療センター センター長 長田 乾 先生)より